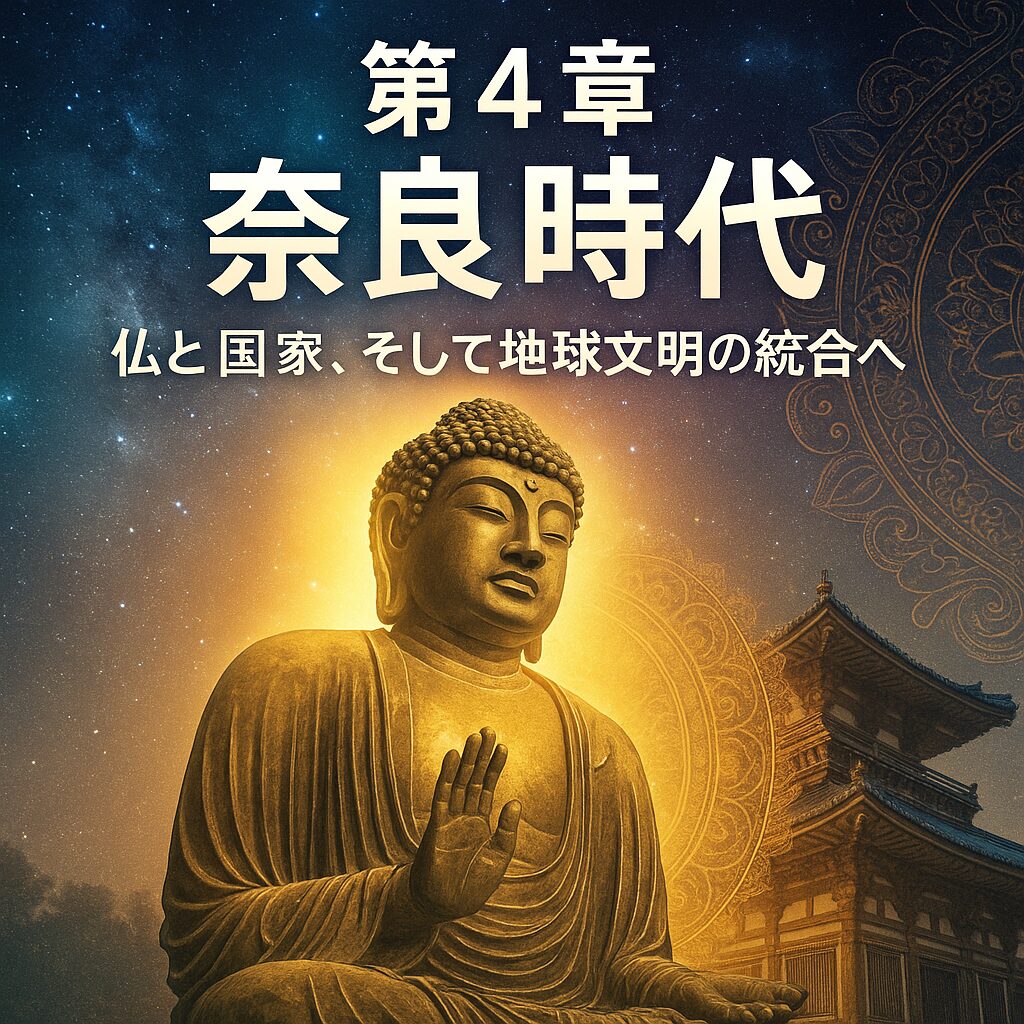日本の神々:高千穂町を訪れてみる

天の岩戸伝説があった。
天岩戸神社の主祭神は「天照皇大神(アマテラスオオミカミ)」である。
普段、なにげに神社に行ってお参りしているが、ほぼこの方が中心となるようだ。
大麻と言われる御札にも、「天照皇大神」と書かれている。
天岩戸神社
令和6年11月17日に開催された、「岩戸下永之内神楽祭」の見学へ行った。
下永之内公民館という田舎の公民館で開催された。

Screenshot
下永之内公民館から歩いて5分ほどの所に「天岩戸神社」(アメノイワトジンジャ)がある。
最初に東本宮に行ったが、天岩戸と呼ばれる大きな岩の洞窟にはたどり着けない。
入口駐車場に警備員がいたので聞いてみると、西本宮もあるらしいことがわかった。
2〜3分歩くと西本宮の境内にたどり着く。
観光客も多いとみえて、石畳が整備されている。

西本宮の鳥居をくぐって神社へ行くと、鍵が掛かっている入口の鍵を開けて、宮司が案内してくれた。
川沿いの歩道を歩いていくと、大きな岩の扉が見えた。
それが、天の岩戸のようだ。
写真は撮れない。
撮ってしまうとバチが当たりそうである。
天照皇大神が洞窟を出た後、引き換えして来ないように、しめ縄が張ってあった。

しめ縄には、7つ・5つ・3つ、と結びが付いている。
七五三(しちごさん)の言われでもあるようだ。
お守りを売っているところで巫女さんに聞いたが、しめ縄の販売は無かった。
正月が近づくとあるのかなと推測してしまう
神楽
霧島神宮の九面太鼓のお面を購入したこともあり、神楽祭への興味が湧いていた。
歳時記カレンダーを見ていたら「高千穂神楽」が目に入ってきた。
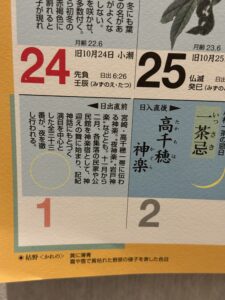
観光情報を見ると、高千穂の夜神楽(たかちほのよかぐら)で高千穂観光協会が紹介していた。
毎晩夜8時から1時間開催されるとのことで、宿泊しなければ見れない。
早速、お宿を探したが、一泊20,000円もする。
ちょっと無理だなとあきらめていたが、昼間に1日でやる神楽を発見したので、これは行くしかないと思って知人を誘って行った。
片道3時間も掛かるが、朝5時出発で8時30分ごろには到着したので、下永之内公民館の方々よりも早く、お客さんとしては一番乗りであった。
「天岩戸神社」から下永之内公民館に帰って、奉納金を少額支払って一番前の席に付くと、ちょうど始まりの時間5分前であった。
なんというタイミングの良さ!
九面も飾られていたが、8面しかない?
面の上の段の黒い箱に入っているのか?
帰りを考えると、ちょうど12時くらいまでしか時間がなくて、最後どうなるかは分からない。
次回の楽しみとしよう。

奉納金を支払ったので、白い紙に名前が書かれて公民館の横に掲げられていた。
ずっと見ていると、おにぎりの無料配布もあった。
朝から何も食べていなかったので、素手でつかんで食べてしまった。
後ほど、割箸も配布された。ハハハ⋯
65歳以上の高齢化率が約45%とという高千穂町であるが、30代くらいの若い男たち、中学生くらいの男子が神楽を舞っており、かなりの新鮮味を感じた。
人口約10,000人。
建物の数や観光客の数からするとかなり少なく感じた。
熊本県と宮崎県のほぼ中央に位置する高原地帯であり、空気もうまい。
目の前を雲が漂っている。

日本の神様
若い頃はなにかと毛嫌いしていた信仰も、還暦を過ぎるとしっかりと知りたくなる。
天照皇大神を中心とした、日本の神様をもっと深く知りたいと思う。
今後、追記していく。
高千穂峡谷
高千穂峡谷は、噂には聞いていて、観光案内の写真で見たことがあったが、初めて行ってみるとなかなか広く、感動的でもあった。


高千穂町
高千穂町は、観光地であることが分かる。
神社も多く、観光客も多い。
外国人も多く見掛けた。

まとめ
天皇陛下のご先祖でもあられる、神々を見て、日本人で良かったと思う。
日本人としての誇りも再確認できた。
八百万の神々が居る「日本」
その中でも「神道」と「仏教」が、日本人の心であると確信している。