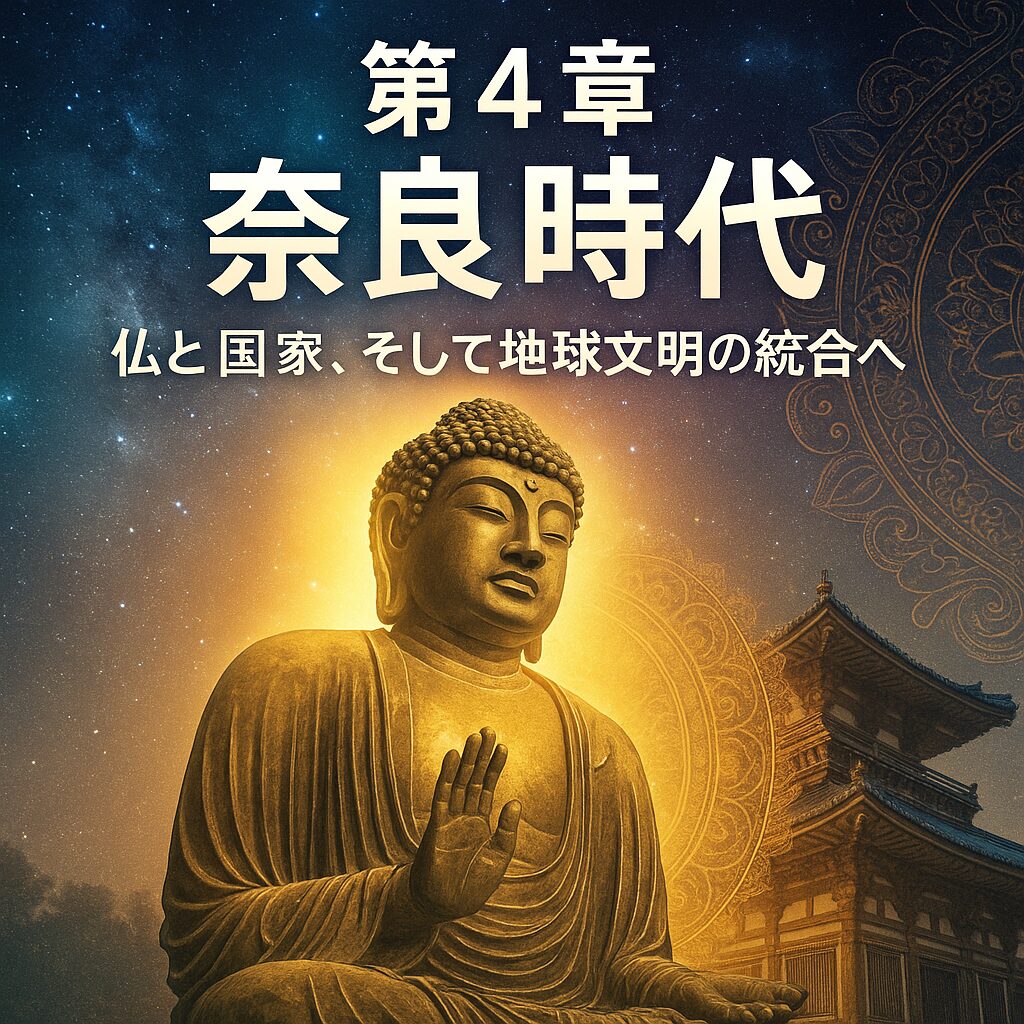神仏習合の歴史|日本独自の信仰が生んだ“神と仏”の共演とは?

神と仏は対立しているのではないかと思っていた
学習していないのでよく分からなかったが
現在自宅には、仏壇があり、その横に神棚がある
今日は、神仏習合にスポットをあててみよう!
はじめに|神と仏はなぜ共に祀られるのか?
日本の神社にお参りしたあと、お寺で手を合わせる——。
私たち日本人にとってはごく自然な行為ですが、これは世界的に見ても非常に珍しい現象です。
この背景には、「神仏習合(しんぶつしゅうごう)」と呼ばれる、神道と仏教が融合した長い歴史があります。
今回は、その神仏習合の歩みを、時代ごとに紐解いていきましょう。
第1章|仏教伝来と神との出会い(6世紀〜)
仏教が日本に伝来したのは、538年(または552年)とされています。
このとき、日本にはすでに自然信仰や祖霊信仰を中心とした「神道(しんとう)」がありました。
ところが、仏教が「外来の宗教」として伝わると、はじめは激しい反発もありました。
物部氏と蘇我氏の「崇仏論争」はまさにその象徴です。
しかし、仏教の知識や仏像の芸術性、高度な文化に惹かれた朝廷は、次第に仏教を受け入れていきます。
この時期、「仏教は神道と敵対するものではない」「神もまた仏に導かれる存在である」という思想が生まれ始めます。
第2章|神は仏の化身? 本地垂迹説の誕生(奈良~平安時代)
神仏習合が思想的に体系化されたのは奈良~平安時代。
このとき登場するのが「本地垂迹(ほんじすいじゃく)説」です。
これは「仏が本来の姿(本地)であり、日本の神々はその仮の姿(垂迹)としてこの世に現れた」とする考え方。
つまり、神は仏が日本人を救うために姿を変えて現れたというわけです。
この思想によって、全国の神社に仏像や仏堂が建てられ、神社の中にお寺がある「神宮寺(じんぐうじ)」が各地で成立しました。
第3章|最盛期を迎えた神仏習合(鎌倉〜室町時代)
鎌倉・室町時代には、神仏習合が日本文化に完全に根付いた時代と言えます。
多くの神社には仏教の僧侶が常駐し、神を祀る祭祀も仏教儀式の形式で行われるようになります。
また、仏教側も民衆に広がるために「神の言葉」を借りて布教するなど、両者は協力関係にありました。
この時代、神社と寺院がセットで運営される「神宮寺」形式が一般的になり、例えば「春日大社と興福寺」「八坂神社と建仁寺」のような一体運営も当たり前でした。
第4章|神仏分離と廃仏毀釈(明治時代)
ところが、明治政府の登場によって、状況は一変します。
1868年、政府は「神仏判然令」を発布し、神道と仏教を明確に分離する方針を打ち出しました。
これが「神仏分離令」です。
この命令によって、多くの寺が破壊され、仏像や仏具が打ち捨てられる「廃仏毀釈(はいぶつきしゃく)」運動が全国で巻き起こります。
1000年以上続いた神仏習合は、強制的に引き裂かれたのです。
第5章|現代における神仏習合の名残
現在でも、神仏習合の名残は全国に残っています。
・神社の境内にお地蔵さんがある
・寺の中に鳥居がある
・「初詣」で神社もお寺も参る文化
・神社名に「宮」ではなく「寺」が入っている場所もある(例:清水寺の地主神社)
このように、私たちの暮らしの中には今もなお、神と仏が共存しています。
これはまさに、日本人が長い時間をかけて育んできた「調和の精神」の象徴ともいえるでしょう。
おわりに|“違いを越えて共にある”という日本の叡智
神と仏——
本来、異なる存在だったこの二つが共に祀られ、信仰されてきた背景には、「どちらかを否定せず、融合させる」日本人ならではの感性があります。
神仏習合の歴史は、「分けることより、つなぐこと」に重きを置いた、日本的な知恵の物語なのです。
現代の私たちも、違いを受け入れ、共に生きるヒントをこの神仏習合から学べるかもしれませんね。
関連記事リンク(内部リンク案)
- YouTubeを見て涙が出た話
- 日本の神々:高千穂町を訪れてみる
- 日本史備忘録(序章):地球人としての記憶・宇宙人との交流へ向けて