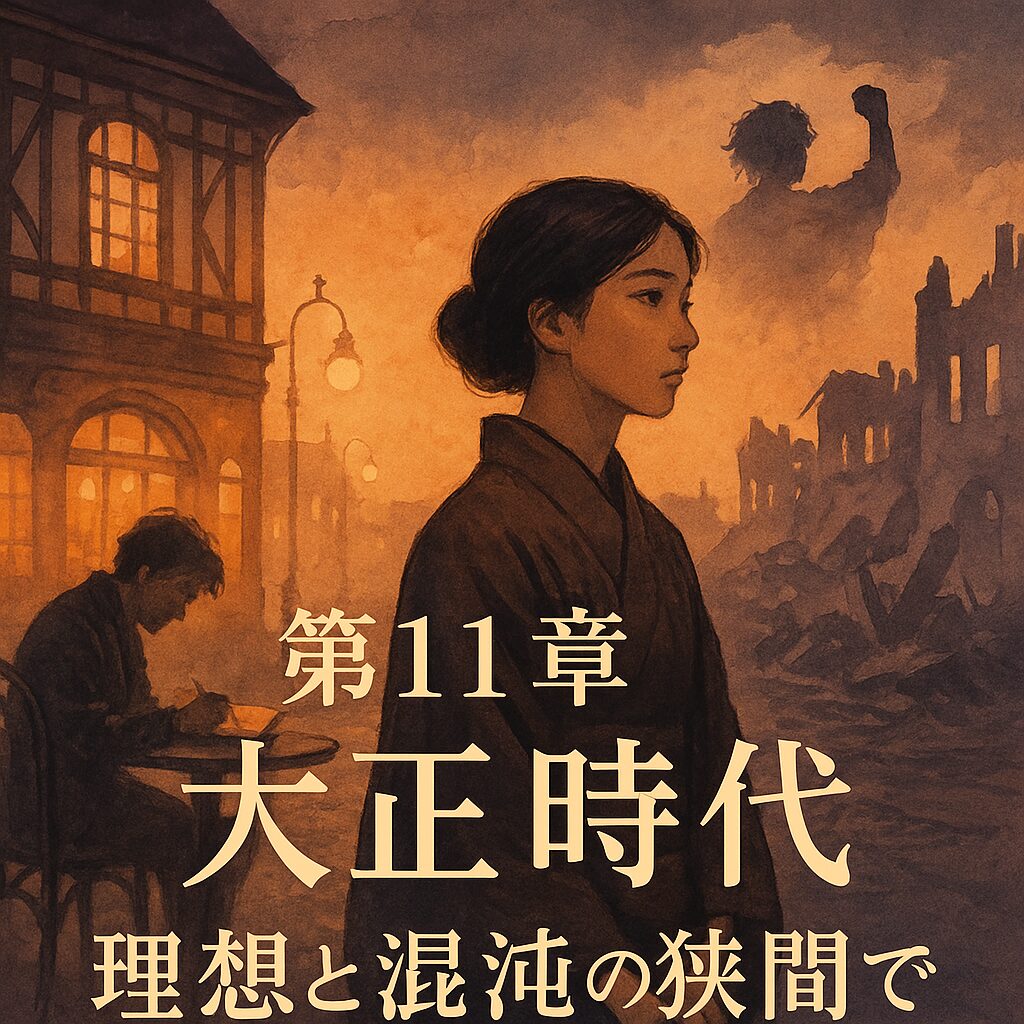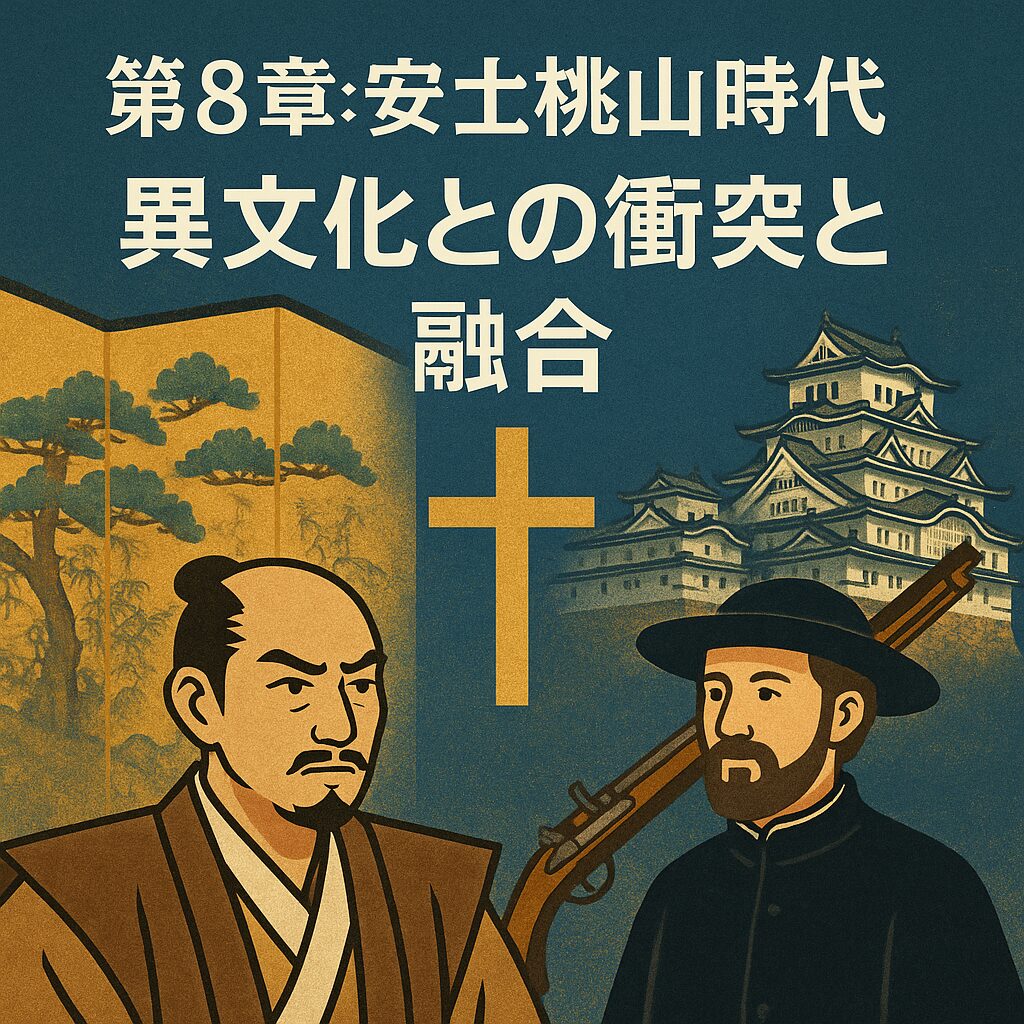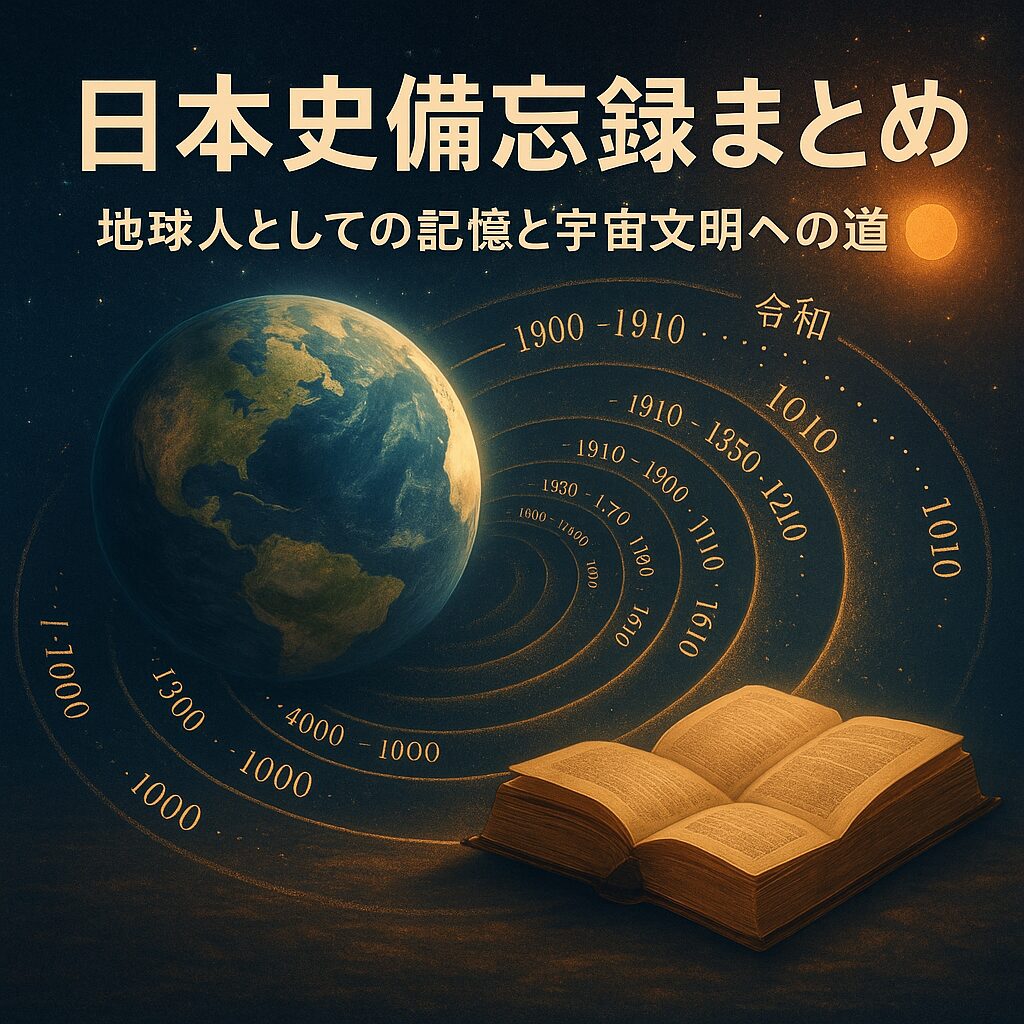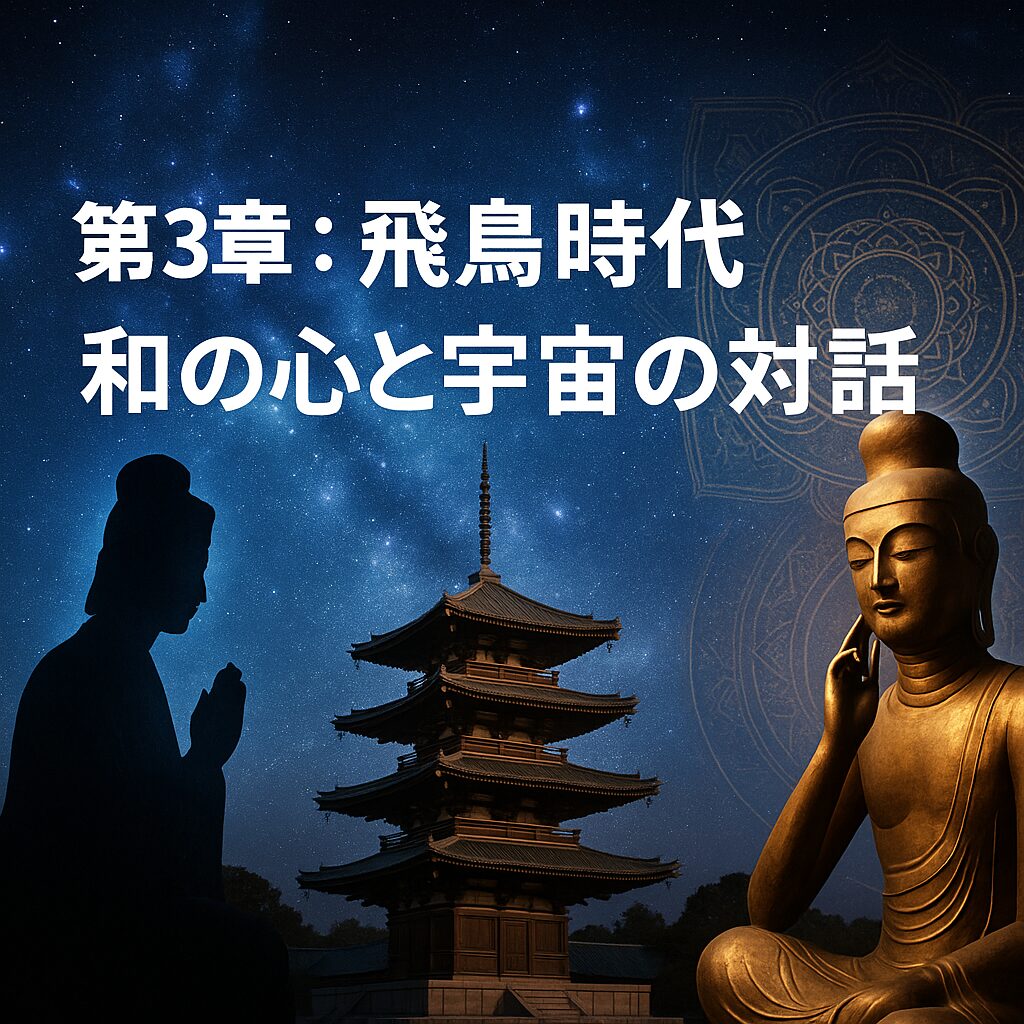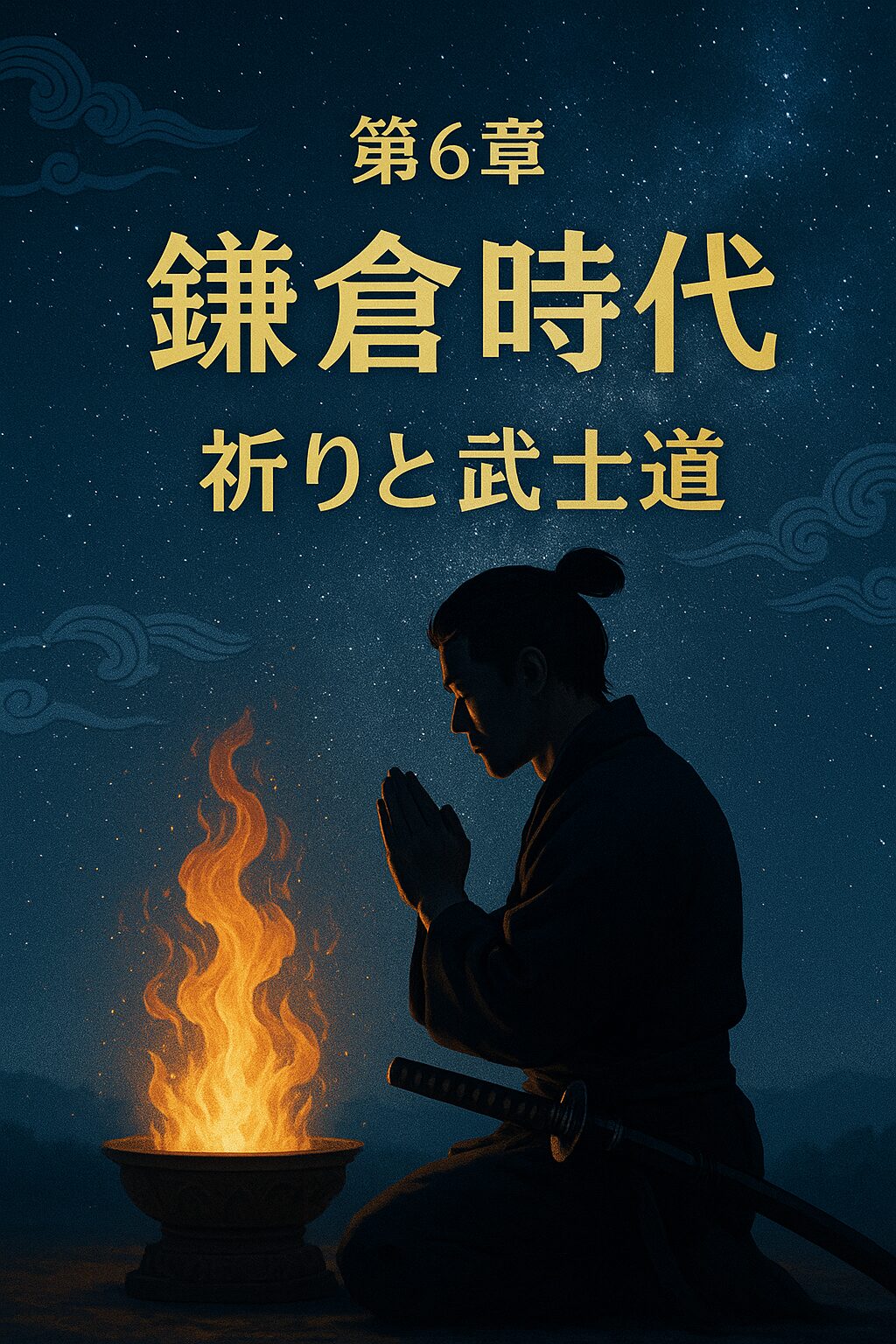日本史備忘録(第12章):地球人としての記憶・宇宙人との交流へ向けて

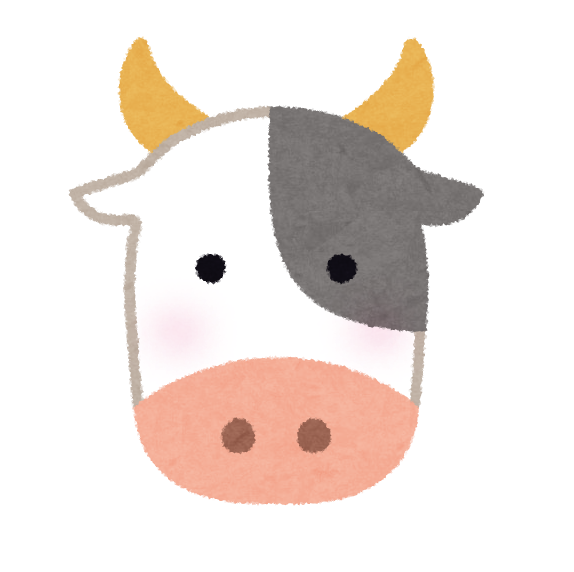
時代は宇宙へと向かっている気がする。
日本人の私は、もっと日本という国を知っておく必要があると思っている。
まずは、日本の歴史を一般的な視点からおさらいしておこう。
これは、自分自身のための備忘録でもある。
第12章:昭和時代(戦前) ― 破壊と制圧、闇を通過することで見える“光の本質”
文明はいつも、光と闇を繰り返す。
そしてその“闇”の中でこそ、人間の「本質」があらわになる。
昭和戦前期(1926〜1945年)は、まさにその闇のピーク。
だが、それは“絶望の時代”ではない。
「光の本質」を探るために、地球人があえて通過した“魂の試練”だったのかもしれない。
◆ 昭和戦前期とは? ― 緊張と破壊の加速時代
昭和初期、日本は大正の理想から一転して「統制と軍国」へと傾いていく。
- 世界恐慌の影響(1929)
- 満州事変(1931)から日中戦争(1937)
- 国家総動員法、教育勅語の徹底
- 太平洋戦争(1941〜)と空襲、戦没者
すべてが、「国という巨大な意思」によって個人が吸収されるような時代。
だが、それは同時に――
地球人が“制圧と破壊の波動”にどう耐えるかを学ぶための訓練だったのではないか?
◆ ファシズムと集合意識 ― 闇に引き寄せられる力
国全体が“同じ方向”へ進んでいくとき、
そこに必要なのは**「共通の幻想」**だ。
- 国体=天皇中心主義
- 忠君愛国=自己を手放す教育
- メディア統制、検閲、言論弾圧
これらは、まるで地球の“集合意識”が闇側に偏ったときのシュミレーションのようでもある。
“善”のつもりで動いた人々が、結果として“破壊”に加担してしまう――
その矛盾が、魂の痛みと成長を生む。
◆ 教育と精神統制 ― 光の仮面をかぶった闇
- 教育勅語:「お国のために命を捧げよ」
- 少年兵、軍国少女、銃後の民
- 靖国神社と“英霊信仰”
- 修身(徳育)= 忠誠心と献身の型にはめる装置
これらは一見「道徳」や「教育」に見えるが、
内実は**個の魂を均質化させる“制圧型教育”**だった。
だが――
そんな中でも、「疑問を持つ魂」「詩を詠む魂」「祈る魂」は確かに存在していた。
◆ 破壊がもたらした“魂の覚醒”
空襲、飢餓、死別――
都市の崩壊と共に、多くの命と価値観が失われた。
けれど、そこから芽吹いたのが、
- **「本当の生とは何か」**という問い
- **「国家とは? 人間とは?」**という哲学的探究
- **「誰かの命を奪う理由とは?」**という倫理への覚醒
破壊の極限でしか触れられない、“根源的な問い”が人々の中に芽生えた。
◆ 芸術と記録 ― 闇の中でも灯された火
戦時下にも芸術は存在した。
それは「許可されたもの」であっても、
そこには**人間の“声なき叫び”**が宿っていた。
- 映画、詩、短歌、童話
- 家族宛の手紙、日記、祈りの詩篇
- 軍靴の音の隙間に描かれた“静かな反抗”
声にならないものこそ、“宇宙に届くメッセージ”である。
◆ 闇を通過することで、人は“光”を知る
この時代を宇宙的に見るならば、
「地球人が“闇のエネルギー”を体験することで、次の次元へのジャンプに備えた」
と言えるかもしれない。
- 自由を奪われるとはどういうことか
- 命の価値とは何か
- 愛とは? 国家とは? 戦うとは?
それを**体験レベルで学ぶために、あの時代が“必要だった”**とすら思えてくる。
◆ まとめ:昭和(戦前)は、“破壊から覚醒への転換期”
一面の闇だったように見える時代。
でも、その闇の中からこそ、光の本質が輪郭を持って立ち上がる。
- 破壊されたからこそ「本物」を求めるようになった
- 抑圧されたからこそ「自由とは何か」に目覚めた
- 声を奪われたからこそ、「祈り」が生まれた
昭和戦前期とは、
**地球人が“光の選択”をするための“闇のレッスン”**だったのだ。
👉 次回予告:【第13章 昭和時代(戦後)】復興と再誕生 ― 瓦礫の中に咲いた“平和という魂の花”
次回はいよいよ戦後。
焦土の中から立ち上がった人々は、どんな未来を描いたのか。
そこには“真の地球人”としての目覚めが宿っている。
お楽しみに!